これはかなりガチなやつだなと思った。【オリジナル小説】【短編】
お昼ご飯は、1人で食べたい。
いつもそう思うわけではない。
でも、会社に来て一生懸命働いた午前中。
お昼休みくらいは1人でご飯を食べて、のんびりと頭を休めて午後に備えたい。
他の女の子たちは、揃ってご飯を食べに言って他愛もない話に花を咲かせている。
仲が悪いわけではないのだけど、仲がいいわけでもない。
けれど、1時間半しかないお昼休みまで一緒にいたいとは思わない。
彼女たちは、どこかのお店にランチに行くから、
私は手製のお弁当を公園で食べるようにしている。
「節約してるから」と言ってはいるし、
10分前にはオフィスに戻って、彼女たちに混ざるようにしているので目に見えた問題はない。
オフィスのすぐそばにある公園に行って、
お弁当を食べて、図書館で借りた本を読む。
これが私に日課だった。
なのに、この男は私の前に立っているのだろうか。
「隣、いいですか?」
「…ええ、どうぞ」
腰を下ろした彼は、紙袋からパンとコーヒーを出して食べ始めた。
確かに他のベンチは埋まっているし、1人で占領しているのは私だけだから仕方ない。
顔見知りではあるし、知らない人に声をかけるよりはいいのだろう。
彼は、同じ会社に勤めている。
私は事務職だが、彼はバリバリ働く営業マンだ。
背は高く、顔もいいし、体も鍛えていてがっしりしているが、表情筋が死んでいるので、ちょっと怖いイメージ。
だけど、面倒見がよくて上司からも部下からも慕われている。
人は見た目ではない、というやつか。
事務的な会話しかしたことがないが、たまに睨まれている気がしてあまり好きではない。
悪い人だとは思わないが、関わりたくはない。
隣に座る彼を気にしないために、食事に集中した。
ああ、今日もいい天気だなぁ。
「美味しそうなお弁当ですね」
話しかけてこないで欲しいと思ったが、同じ会社に勤めているのだから悪態をつくわけにもいかない。
「ありがとうございます」
「ご自分で作っているのですか?」
「ええ、節約です」
当たり障りのない会話。
まあ、向こうも気を遣って話しかけただけだろう。
「そうなんですか」
「拙いですけどね」
早く立ち去りたいけれど、まだ半分も食べていない。
「つかぬことをお聞きしていいですか?」
「なんでしょう」
「あなた、副業してますよね」
「…うちは副業は禁止してませんよね?」
「ええ、きちんと申請すれば」
「そうでしたっけ?」
ああ、どこかでバレて確認と釘を刺しにきたということか。
副業の内容までバレてるのかしら。
彼は横に置いてあったもう1つの紙袋から何かを取り出した。
「これを書いたのが、あなたですよね」
確定事項として聞いてくるということは、裏が取れているのだろう。
否定しても意味がないか。
「そうですね」
めんどくさいことにならないといいのだけど。
「で?私が小説家だとしてなんですか?タカリですか?ヒモになりたいんですか?」
思い切り睨みつけると、彼は驚いた顔をした。
「いえ、デビュー前からファンなので」
「は?」
デビュー前というと、趣味でネットに投稿していた時から?
よく見ると、彼の耳が赤くなっている。
え、なに。
ちょっと可愛くないか。
「数年前、業界に通じてる知人が作者の写真を見せてくれて」
「その直後に、あなたが入社してきたんです」
顔出しなし、年齢性別などを“一応不詳“にしているのに、どこで出回るかわからんものだ。
「ずっと気になって声をかけたかったんです。隠していることだからと諦めていたのですが」
「先日発売された新刊が素晴らしくて、我慢できなくなってしまいました」
こんな時、どんな顔をすればいいの。
恥ずかしいような、照れるような。
というか、ずっと知っていた?デビュー前からファンだった?
「えっと、ありがとうございます?」
「すみません。言ったらどんな顔して仕事をしていいかわからなくなってしまうと思ったんですが」
彼は「それだけです」と言って、食事の途中で席を立ってしまった。
たまに睨まれていたのは、そういうことか。
会社にバレたら退職して小説だけで食べていこうと思っていたのだけど。
彼なら心配ないだろうという謎の確信もあったし、
これからどういう反応をされるのだろうという期待もある。
とりあえず、お弁当を食べ終えたら考えよう。
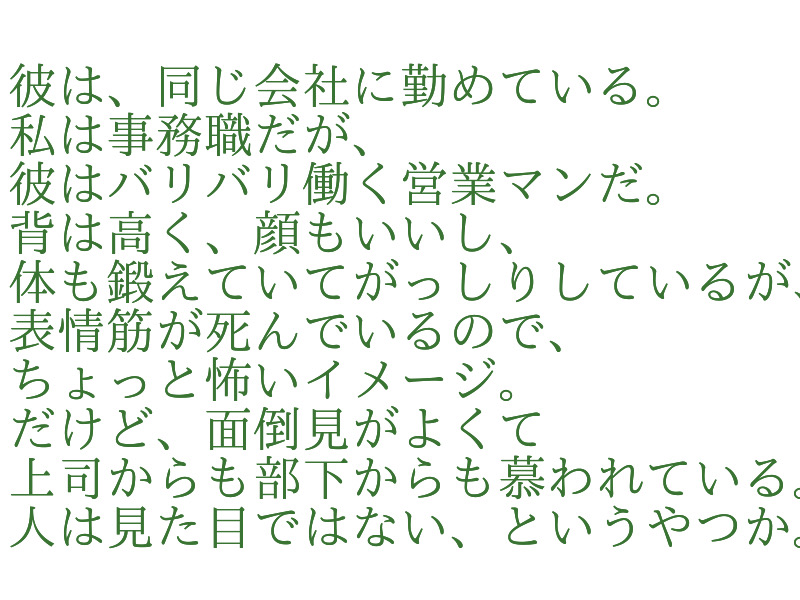

楽天ポイントモールは、「くじ」や「ゲーム」で楽しくポイントが貯まります!!

楽天市場で色々買って、ポイントどんどん貯めてます!!

「モッピー」
動画を見たり、ゲームをしたり、アンケートに答えたり。
地味にコツコツポイント貯めてます!!







「ワラウ」
毎日、テレビ見ながらスマホポチポチしてゲームしてポイント貯めてる!!






